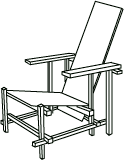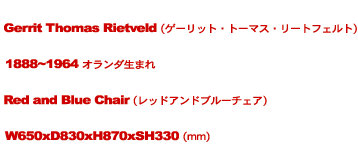見るからに座り心地の悪そうな椅子。背板が赤く、座板は青く塗られていることからレッドアンドブルーチェアの名で呼ばれるこの椅子は、1918年にデザインしたもので実際には赤と青に加え、角材は黒檀色に塗られ、その木口には黄色が配されていて、この黄色が点々と浮き上がって見えるのも、この椅子の特徴の1つとなっている。
座りにくそうだというのは、板と棒による、そっけない角張った構造に対しての直感的な想像であって、いざ座ってみるとどうしてなのか、なかなかの掛け心地。背と座の的確な角度が寄りかかるときのゆったりとした気分を生み、肘の幅、肘の先端の出具合の程よさと肌触りとが、落ち着きと安定感を感じさせてくれる。
長時間座ると、背中とお尻のあたりが痛くなってくるのは平板のままの背と座面であるがゆえにいたしかたない。だから、実際に使うとなると、毛布を掛けたり座布団を置いたりしなくてはならない。しかし、そうするとこの椅子の持ち味である、板と棒の構成美や赤や青などの色彩の美しさが楽しめなくなってしまう。さりとて、痛くなるのを我慢して座り続けるわけにもいかないし・・・。日常生活のなかに美を身近に置いて暮らすことの矛盾とでもいうべきか、辛さとでもいうべきか。いっそのこと、飾り物のオブジェとして置くほうがいいかとも考えたが、それにしては大きすぎるし、困ったことだ。
この椅子は、矩形断面の角材を水平・垂直に交差させ、それを小さな丸棒の太柄を使って結合させることにより、単純明解な構成美を表現した椅子である。フォルムを人体に対応させるためには曲線の使用によってデザインするという椅子づくりの一般的な姿勢に対しこの椅子は100ミリ単位のグリッド(格子)をもとにその3分の1の長さの33ミリをモデュール(寸法上の基準)とし、このモデュールの正数倍の活用によるデザインで人間の寸法に対応させようとしている。このグリッドの考え方とモデュールの思考法を家具に導入したことは、その後の近代デザインに大きな影響を与えている。
|
|
参考文献:椅子の物語-名作を考える-、現代の家具と照明、洋家具とインテリアの様式 |