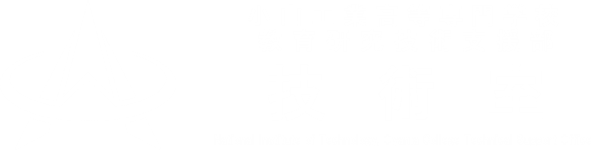| < 前の記事 | | | Web講座TOP | | | 次の記事 > |
初心者向け はんだ付け講座 - 第1回「はんだ付けとは」
投稿者:2G 加藤
はんだ付けは、電気電子回路を組み立てるために無くてはならない技術です。
皆さんの身近にある、家電製品やコンピュータ、おもちゃなど、ありとあらゆる物の回路部分は、プリント基板の上に部品をはんだ付けして作られています。
中学校の技術の時間でも学習する、このはんだ付けですが、実は意外と奥の深いものです。
はんだ付けの理論(1
はんだ付けを難しく説明すると「加熱された材料の間にはんだを流し込み、材料を溶かしたり変形させることなく接合すること。」となります。金属同士をつなげる「溶接」の一種です。
電気電子回路のはんだ付けでは「スズ(Sn)」と「鉛(Pb)」を合わせた「Sn-Pb合金はんだ」がよく使用されます。この合金の融点(熱によって溶ける温度)は183℃のため、「はんだごて」を使用して、材料をこの温度以上に熱してから、はんだを溶かして流し込み、接合するのです。
はんだ付けは、もし適当にやっても意外とくっついて、電流が流れるものです。しかしその時の基板とはんだの間には、何が起こっているのでしょうか?
加熱された材料に溶けたはんだを供給します。ただしこの瞬間は、材料とはんだは馴染んでおらず、ただ材料の上に載っているだけです。
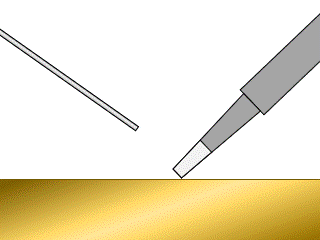
材料とはんだが馴染むと、液体のように平らに広がります。この状態を「濡れ」といいます。
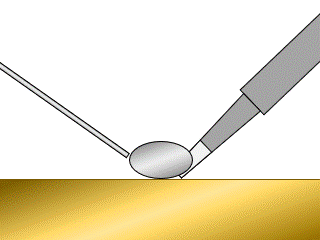
この時の材料とはんだの境界面では、まず材料の中にはんだが「拡散」します。材料が銅(Cu)の場合ははんだの中のスズ(Sn)のみが選択拡散し、Cu3Sn合金を作ります。
するとはんだの中へ、材料が拡散してきます。この現象は、液体の中に固体が溶けだすので「溶出」と呼ばれます。
はんだごてを離して冷却されると、材料の表面に溶出した銅が「再結晶」して合金となります。この合金はCu6Sn5で、合金層の厚さはわずか数μm(マイクロメートル)程度です。
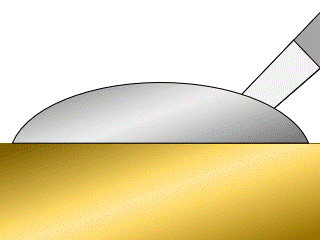
実際の作業では、この工程が1~3秒程度で終了します。
さて、ここで大切なのは「合金層」がしっかり出来ていない場合は、うまく電流が流れないということです。
しかも見た目には違いが分かりづらく、少しだけ電流が流れたとしても大電流は流せなかったり、電流がはしっかり流れていても電磁的なノイズが発生したりするため、たちが悪いのです。
また合金層は基本的に薄いために、外から衝撃が加わるとはんだ(部品)と基板が剥がれてしまうこともあります。
こういったトラブルが起きないように、きちんとした手順ではんだ付けを行い、しっかりとした合金層を作る必要があるのです。
はんだ付けに必要な道具
はんだ付け作業に必要な道具を説明します。道具はホームセンターや工具店、ネット通販などで購入できます。
はんだごて
材料を加熱するために使います。これは非常に多くの種類があり、安いもの(千円程度)から高いもの(数万円)まで値段の幅もあります。
すこし体験してみたい、もしくは初めてはんだ付けを行う人は、安いもので十分です。家にすでにはんだごてがあれば、まずはそれを使いましょう。新たに買うとしたら、ニクロムヒータータイプの一番安いものでOKです。
下の2つは、有名メーカーの長年定番とされているモデルです。
はんだごてにはワット(W)数があります。これはヒーター(加熱部分)の強さを表しています。一般的な電気電子回路を作る場合は30Wくらいのものが良いとされています。
小山高専 電気電子創造工学科の実験実習では、少し高級なタイプのはんだごてを使っています。それが以下のモデルです。
このはんだごては、ヒーターに「セラミックヒーター」を採用していて、電源プラグを入れてから速く温まるのが特徴となっています。
また本体に温度調整ダイヤルがあり、熱くなりすぎることがありません。
ダイヤルを調整することで、金属部分が大きい部品から、熱に弱い半導体部品まで、一本であらゆる状況に対応できるのが便利です。
はんだごて台
はんだごてを買うと簡易なこて置きが付いてくることもありますが、重さのあるしっかりしたものを別に用意した方ががいいです。
なぜなら、通電中のはんだごては約350℃程に熱くなるため、間違って触って火傷したり、コードを引っかけて机やカーペットを焦がしたりといった事故が起きないようにするためです。
また別売のこて台には、こて先クリーニング用のスポンジ置き場が大抵付いています。こて先のクリーニングは非常に重要ですので、使いやすいところにあると便利です。
糸はんだ
電気電子回路用の糸はんだは、中心に「フラックス」と呼ばれる促進剤が入っていて、はんだ付けがやり易くなっています。フラックスは「ヤニ」とも呼ばれます。
フラックスは、はんだと一緒に溶けて、金属部分を洗浄してはんだを付きやすくしてくれます。また表面張力を低下させ、濡れ広がりを助けてくれる作用もあります。
ホームセンターやネット通販などで購入する場合、まずは20gくらいのスティックタイプを選ぶと良いでしょう。もし沢山はんだ付けをするようになったら、500g~1kg巻きなどの大きいタイプもあり、こちらのほうがお得です。
線の太さも色々あります。電気電子回路用で一般的なのは、直径1.0mm又は0.8mmのものです。(φ(ファイ)1.0, φ0.8とも表現します。)とても小さい部品や狭い部分をはんだ付けをする場合には、より小さい径のはんだを使うこともあります。
種類分けの一つに「鉛入りはんだ」と「鉛フリーはんだ」があります。
古くからはんだの成分として使用されてきた鉛は、大量に摂取すると人体に有害であり、疲労感や頭痛などの症状がある「鉛中毒」を引き起こします。
そこで近年では鉛を使わない「鉛フリー(Free)はんだ(PbF)」というものが開発され、製品として販売するもの、特に外国への輸出を考えた製品には、こちらのほうが一般的に使われるようになりました。
しかし鉛フリーはんだは融点が約217℃で鉛入りはんだより約35℃高くなる事により、加熱不足を引き起こしやすいことと、濡れ広がり性も鉛入りより悪くなることにより、はんだ付けがやり辛くなってしまいます。
初心者がはんだ付けを練習したり、個人で使う回路を作ったりする分には、鉛入りはんだを使うほうがおすすめです。
ラジオペンチ・ニッパー・ピンセットなど
はんだ付けをした後に余った部品のリード線を切るためには、ニッパーが必要になります。
また部品を加熱しているときにズレてしまい、位置を直したり一時的に支えたりする時に、素手で触ってしまうと火傷してしまいます。そういう時は、ラジオペンチやピンセットで摘まむことで安全に作業します。
その他 - はんだを修正するための物
間違って部品を付けてしまったときや作り直しをするときは、はんだを再加熱して溶かし、いったん除去します。
その場合「はんだ吸い取り線「ウィック(Wick)」と呼ばれる銅の編線に吸わせることで、部品や基板からはんだをきれいに除去することができます。
また「はんだ吸い取り器」という、空気を高速で吸い込む際に溶けたはんだを一緒に吸い取ってくれる器具もあります。こちらのほうが繰り返し使えるため、長い目で見ると経済的です。
溶け残ったはんだが付いた状態で、部品を無理やり外したりすると、部品や基板の銅箔パターンを壊してしまうこともあるため、こういった道具を使って丁寧に外すのが大事になります。
参考文献
- トランジスタ技術SPECIAL No.129 見ればわかる!正統派のはんだ付け[動画DVD付き]:トランジスタ技術SPECIAL編集部, CQ出版社(2015.1.1)
| < 前の記事 | | | Web講座TOP | | | 次の記事 > |